| HOME | GALLERY1 | GALLERY2 | TEXT | LINK | WEBCLAP | ←お気に召したなら拍手をひとつお願い致します |
第五話 天に星、地に花
血のように紅い夕暮れ。
辺りをすべて朱に染めて陽が沈もうとしている。
微かな風に乗って季節はずれな金木犀の香りが漂って来た。
殺生丸は不快気に、揺らぐ空気を睨みつけた。
収斂した気が逢魔が時の幻影のように人型を成す。
顕れた人影は優雅に扇を使い、半ば口元を隠すように声を発したが、凜とした声音が耳に届いた。

「これは犬の御曹司、暫く見ぬ間に益々麗しくなられた。
美しいものを好むわが一族の中にも、あなたを欲しがるものが後を立たないと聞くが、なるほどこれは頷ける」
だが、そう言う相手こそが息を飲むほどに秀麗な姿の青年であった。
眸は海の青より深く、長く垂らした髪は、この時代の日ノ本にあっては人間は勿論のこと、妖しであっても稀なる豪奢な金色。
朱鷺色の狩衣をふぅわり纏った美しい姿から、焚き染めた香であろうか、金木犀の香りが漂ってくる。
この美青年の
「そのような下らぬことを言いに来たのではあるまい。
〝京の鬼〟がこの東国に何用だ」
「迦具土の媛・・・それはどういう意味だ」
「おや、犬の御曹司はご存じないのか?
「迦具土の神・・・
誕生の折り、母神を己が炎で焼き殺してしまったという逸話であろう・・・
それが姉上にどのような関係があるというのだ」
「愛する妻を死に至らしめたことに激怒した父神は、迦具土を切り殺した・・・
もっとも〝犬の長〟は媛を刃に掛ける前に正気に戻ったそうだが」
「父上が、姉上を刃に掛けようとしただと・・・たわけたことを」
「噂です、単なるね。
実のところは他愛ないことに尾ひれがついたのでしょう。
まあ、火の無いところに煙りは立たないとも言いますがね」
「きさまが何も無いところに、後足で土煙りを立てているのではあるまいな。
つまらぬ話はせぬほうが身のためだぞ」
「それは心外ですね、犬猫でもあるまいに。
おや失礼、紛うかたなき犬妖怪であられたな。
ですが、いちがいに噂話も侮れぬものです。
あなたが半妖の弟に、ばっさり腕を切り落とされた、という噂はどうやら真実のようではないですか。
血を分けたものどうしで争われたか。
いやはや、犬族は情が深いと聞いていたが、可愛さ余って憎さ百倍なのですか」
殺生丸が減らず口を
殺生丸と〝鬼の長〟彩扶錏の間に、麒麟を伴った銀妖がふわりと降り立った。
「それぐらいにしておけよ〝
次はその口に撃ち込むぞ!」
「姉上」
「これは銀花媛、比度は無事の御帰還、祝着至極に存じます」
銀花の右手を取ると、優雅に腰を折りそっと指に口づける。
「〝鬼の若長〟にあられては、先代から
今や〝京の鬼族〟は並ぶもの無き権勢と聞き及ぶ。
まこと頼もしきことだが、手腕とはまさか、そのよく回る舌先のことではあるまいな。
うまく周辺蛮族やうるさい
「これはまた辛辣な。
どうぞ先程の言はお許し頂きたい。
同じ身の上のはずが、気楽になされている弟君が羨ましくて少しからかったまで。
わたしがあなたに含むところが無いのは、よくご存じでしょう?」
「それにしては皮肉に過ぎる物言いであったようだが」
「それはあなたもいけないのですよ。
わたしに何の断りも無しに旅に出られた」
「おまえに断わらねばならぬ理由があったかな」
「またそんな。
日々の気苦労とあなたの仕打ちで少々ひねくれたとしてもお責めになるな」
「一族を束ねるのは骨が折れるか」
「ええ、それはもう。
敵ならば力で済むところが、身内においては始末が悪い。
齢経たものは口うるさいだけでなく、とかく頑迷で困ります」
「かもしれぬが、永く仕えてきてくれたもの達は敬ってしかりなのだ。
このところの〝
その手腕は本物だな」
京の闇の世界、妖しどもが集うもう一つの都は〝亨〟と呼ばれていた。
「実のところ、流入してくる妖しが多すぎて、秩序を保つのもままならぬというところです」
「鬼族の庇護のある〝亨〟は力無い妖しには住み安かろう。
だが、過密になると表に転び出るものも多くなり、人間との軋轢も増えような。
確か鬼族の悲願は表と裏、共々の京を
「今敢えて表の京までどうこうすることもないと思うのですが、それこそ古参がうるさい」
「ほう、当代の〝鬼の長〟は人間の京に執着せぬか」
「表の京を手中にするにはまず、その守りを何とかしなければいけない。
ですが今、それにかかずらわっている余裕がないのが現状です。
それに、物事には必ず陰と陽があるように、京も表と裏の世界、それで均衡がとれているのではないでしょうか。
やるならば相応のやりようもあるが、京という地は気脈地脈が複雑に絡み合っている。
へたにまぜ返しては取返しのつかぬ混沌を創ることになりましょう」
「そうだな」
彩扶錏の言葉に銀花は小さく微笑む。
陰と陽、片方がもう一方より強くなる、または飲み込んでしまうというのは彩扶錏の言うように、大きな歪み亀裂が生じる。
京という地にはとてつもない霊的力が存在する。
〝京〟と〝亨〟が今のところ上手く均衡がとれているのは、〝亨〟が膨張するのを鬼族が整然と秩序を持たせていることに依るところが多い。
無闇なことをすればそれが崩壊し、日ノ本の中心たる京から放射状に混沌が広がり、総てが呑み込まれていくことになるだろう。
だが、京に永く住みその霊的力をより感じているはずの鬼族の中でも、そのことに気付いているものは少ない。
ただ単に京を征服したいと望むものが多いのだ。
「で、その繁忙な〝鬼の長〟が、自らこの東国まで
「勿論あなたを迎えに来たに決まっておりましょう」
「だから我に何用か」
「あなたの永の不在は本当に気を揉みました。
が、こうしてお戻りになったあかつきには、いよいよ婚礼の準備を推し進めることが出来るというもの。
そのためにお迎えに上がった次第です」
「誰の婚礼だ」
「あなたとわたしですよ」
「はあぁぁ?」
「そのような素っ頓狂なお返事をされては傷つきますね。
あなたとわたしは
良い年頃となった今、婚礼の儀を執り行い、夫婦となって永遠の愛を誓い合うのが道理」
「なにが道理だ!
婚礼の儀など行わぬ」
「面倒だとおっしゃるのなら儀式は後回しでもかまいません。
ではまず今夜にでも愛を契りましょうか」
「契らぬ!」
「今宵はいけませんか」
「今宵も明晩もだ」
「では、どうしろと・・・
まさか銀花、いくら日が暮れてきたとはいえ、まだ残光のある内から、まして衆目のあるここですぐさま致せとおっしゃ
るか!
いやいや、あなたがお望みならば、わたしとしてはやぶさかではないが」
「誰がそんなことを言っている・・・
よいか、彩扶錏」
間近に相対して噛んで含めるように言い渡す。
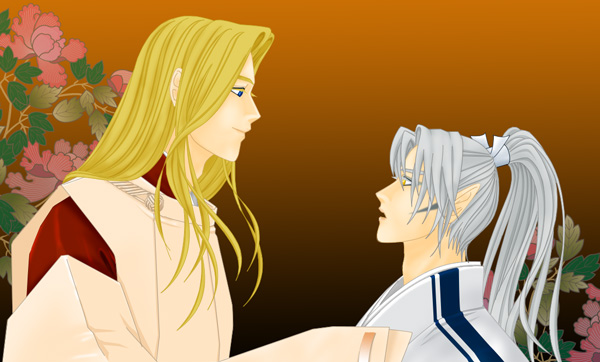
「確かに、父上と鬼の先代の間で和睦が交わされた折りに、その証しとして我らを許婚となされた。
だがその後、鬼族はこちらの領地に無断で分け入り、あまつさえ騒ぎまで起こしたのを覚えておろう。
その時点で和睦も婚約も、すっぱりきっぱり
「あなたは昔から愛らしかったが、さらに美しくなられたな」
「おまえ、我の話を聞いているのか?
もう我とおまえの間には何の絆もないし、しがらみすら微塵もない」
「永い間、行き方知れずだったあなたを待っていた甲斐があったというもの」
「だからもう待たずともよい。
さっさと他から妻なり何なり迎えよ」
「ああ、その花びらのような唇に触れてもよろしいか」
「きさま、まったく聞いておらぬな!
それとも聞く気がないのか、その耳は飾りか!」
「うふふ、あなたの小言は心地よい調べのようだ。
ですが、出来うるならば、甘い喘ぎをお聞かせ願いたい」
「おまえという奴は・・」
「あぁ、あなたの喘ぎはどれほどに甘美でありましょう。
想像するだに躯が奮い起ちます」
「想像するな、起たせるな!」
「銀花、わたしは連続でしたら三回までは大丈夫ですが、間に少し猶予をいただけるなら、
朝までだってお応えできる自信があります」
「これが、かごめの言っていた〝セクハラ〟発言か・・・」
「たとえこの世で、きさまと我だけになったとて、断じてきさまとは契らぬ!」
「つれないことを・・・
あの初夏の午後のことを憶えておられますか?
わたしは忘れられません。
滝のほとりでふたりして躯も心も、しっぽり濡れた仲ではないですか」
「誤解をまねくような言い方をするな!
あれは滝壺に飛び込んだだけであろう」
「今宵はわたしの胸に飛び込んで下さい」
がばとばかりに銀花に抱きつこうとした彩扶錏めがけて、殺生丸の毒華爪が繰り出された。
先程の銀花が放った妖気の矢は、銀花の本気ではなかったが、微ながら彩扶錏の頬を掠めていた。
が、至近距離からの殺気溢れる殺生丸の爪は、ひょいと難無く躱された。
「おやめなさい、殺生丸!
あなたは義兄を殺すつもりですか」
「だれが義兄だ!
次は外さぬ、覚悟するがいい」
「殺、やめておけ。
仮にも京の〝鬼族の長〟だぞ」
「お止め下さるな姉上。
今ここで、こやつの息の根を止めておかねば、必ずや遺恨を残す気がいたします」
「〝鬼の長〟に何かあれば、鬼族と
「その鬼族とやらが知るところとなれば、でございましょう、銀花様。
屍を闇に
地中深くに埋めるか、海中に沈めるか、何でしたら
極めて不穏当な発言は、銀花の傍らに控えている長身の青年であった。
普段にはない険しい表情をして
「おや、それなる強い霊気を発しているは、もしや・・・
なるほど、麒麟をお連れになったという噂も本当なのですね」
「ああ、我の麒麟〝蒼鉛〟だ」
「麒麟と言えば霊獣のなかの霊獣。
四神、東の青竜・西の白虎・南の朱雀・北の玄武にも匹敵する霊力があるとか」
「彩扶錏、蒼鉛を都の守りの四神と戦わせようなどと、よもや考えるなよ」
「まさか、麒麟は霊力は強くとも、慈悲の霊獣ゆえ戦いは出来ませんでしょう。
ですが、慈悲の獣とは思えぬ問題発言ですね」
「慈悲をかけるような相手ではないと、わたしの本性が言っています」
「ほう、見たところ黒麒麟のようだが、その色と同じに黒いものを裡に囲っているのではあるまいな。
どんな本性だか愉しみなことだ」
「少なくとも、
「まったく、小生意気な小僧がもうひとり増えたということですか、面倒な」
「鬼、小生意気な小僧とはわたしのことではあるまいな!」
「おや、よくおわかりで」
「今直ぐ始末をつけてやる」
「殺、いちいち彩扶錏の言うことに反応するな」
「銀花様、ここはやはり、弟君のおっしゃるように早々に始末をつけておいた方がよろしいかと存じます」
「蒼鉛までそんなことを・・・」
「危ない麒麟ですね。
銀花、これをお側に置くのは問題ですよ。
優しげな様子をして、何時豹変して襲ってくるやもしれません」
「誰が豹変ですか!あなたと一緒にして欲しくないです」
「彩扶錏、慈悲の霊獣をも苛立たせるおまえの方が問題だろうよ」
銀花は、今にも飛び掛からんとする殺生丸と、ぞっとする冷ややかな微笑を張り付かせた蒼鉛を、やれやれと制する。
「確かに先程あなたが言われたように、形式的にはもう許婚ではないとしても、わたしの裡では未だあなたは許婚。
改めて我が妻にお迎えしたい」
「彩扶錏、おまえが欲しいのは我の力、いや犬族の血であろう。
琵琶の湖は鬼族にとっても重要なもの。
それと通ずる伊吹山を欲するも、山懐にある犬族の本殿が目障りだ。
我を娶り犬族と血縁を結べば流血することなくあの山を手中に出来る、そう
だが生憎、我は犬族にあっても異端。
今、伊吹山の本殿を牛耳るは
が、我が鬼族に嫁げば、厄介払が出来たと安堵こそすれ、決して鬼族の傘下に入ることはあるまい。
まこと伊吹山を欲しいなら、犬族の本殿など問題ではない。
伊吹のお山と気脈を通じることが出来るのは総領たる殺生丸ただひとり。
我ではなく殺を娶ることが早道だな」
「・・姉上」
「あなたは少し変わられたな。
わたしが、政略や野望のためにあなたを妻にと望んでいると本気でお思いか。
そんなことも分からぬ、あなたでもあるまいに・・・
冥界の父君もさぞご心配であられよう」
「父上が・・・心配・・か・・・
〝鬼の長〟おまえがまこと我を欲するというなら試してやろう。
首尾よく我を受け止めること適ったなら、おまえが望むもの総てを我が力でもぎ取って、持参金代わりに献上いたそ
うぞ。
伊吹の山も京の都も、この日ノ本であってもな」
銀花は艶然と微笑んではいたが、その貌はまるで血の通わぬ能面のようであった。
彩扶錏の背に
睦まじく抱合っている
彩扶錏の貌は愉悦ではなく苦悩に歪み始めた。
だが、銀花の腕を振り払って逃れようとはしない。
優美な貌が蒼白に変わり、自我が命が蝋燭の灯のように揺らぎ始めているのが殺生丸にも蒼鉛にも分かった。
とその時、彩扶錏の唇の端から一筋血が流れ、現実的な痛みに眉を顰めた。
唇を離した銀花は、崩折れるように地に腰を落とした相手に冷たく言い放つ。
「莫迦が・・・・・どうやら無理のようだな」
そっけない言葉とは裏腹に、その貌からは先程の硬質なものは拭い去られ、いつもの銀花に戻っていた。
そして金色の眸の奥に、僅かに傷ついたような色が過った事を、彩扶錏は霞む視界の端に捉えていた。
彩扶錏が何とか事なきことを見て取ると、銀花は蒼鉛の腕を取り飛び立った。
後を追おうとした殺生丸は振り返えると、言い置く。
「京に帰れ、そして二度とこの東国に来るな!」
殺生丸の姿が見えなくなると、彩扶錏はどさりと仰向けになり、盛大にひとつ息を吐いて眸を閉じた。
「姉上、父上が姉上を刃に掛けようとなさった、というのは本当の事なのですか?」
「ああ、そうらしいな。
我は赤子だったゆえ憶えてはおらんがな」
「あの父上がそんな事をなさるとは・・・・」
「それだけ我が母に対する愛情が深かったということであろう。
聞くところによれば、母を娶るにあたって相当な反対にあったそうだ。
愛するものを失っての一時の気の迷いで、われを忘れられたのであろうよ。
父上は我を慈しんで下さったよ」
「はい、姉上が旅立たれた後、何時もご心配になられておりました」
「・・そうか・・・」
《憶えてはおらん》
そう殺生丸には言ったが、強大な力を持って生まれたゆえか、銀花はその時のことを朧げながらも憶えていた。
そして振り被ってくる煌く白刃と、見下ろす冷たい眸だけは、はっきり憶えていた。
それが父であったと後に知った。
が、それにも増して、同じ邸に暮らすようになって時折かいま見るようになった、悲しみを湛えた父の眸の色が哀しかった。
それは少しずつだが確実に、銀花の心の奥底に消えることのない傷を穿っていったのだった。
「どうなさいました、銀花様」
寂しげな主の横顔を慈愛に満ちた眸の麒麟が見詰める。
「蒼鉛、我は弱虫なのだ。
謀に利用されるを厭い旅に出た。
だが本当は、父上に疎まれるのが怖くて逃げ出したに過ぎん。
あの時、我の心がもう少し強ければ父上のお側にいられたのだ。
そうすれば父上をお守りすることが出来たであろう。
疎まれようが何であろうが、いや、お側におれずとも父上が生きておいでになる、ただそれだけでよかったのに」
「銀花様・・・」
「せんないことだな・・・」
「銀花様、けれどそのお陰でわたしはあなたと巡り逢えた。
どんな時も、何があってもわたしはお側に居ります。
ですからもう、過ぎた時を悲しまないで下さい」
「そうだな・・・」
膝枕に眸を閉じた主の髪を、麒麟は優しく手櫛で梳いた。
蒼鉛には、本当に銀花の父が、銀花を疎んじたのかは分からない。
親を持たない麒麟にとって、親子の情というものは範疇の外だった。
麒麟は女仙に慈しまれて育つ。
もうひとつ、麒麟には生まれながらに付き従う女怪がいる。
女怪は麒麟の卵果と同時に生まれ、その麒麟だけを生涯慈しみ守り仕える。
親子の情はそれらに近いのだろうと思っている。
だが、蒼鉛も特異な誕生のために女怪を持たない。
そして、慈しんではくれたが女仙達との間にも隙間があった。
その誕生の境遇に於いて、銀花と蒼鉛は似ていた。
蒼鉛にとっては愛しいばかりの主を、その父が疎んじたとは到底思えなかったが、問題は、真実ではなく、銀花がそう感じているということだった。
天の星のように気高く強く、優しく美しい地上の花。
けれど、心の奥底に傷つき涕いている小さな子供を住まわせている。
《守ってあげたい、あなたを悲しませるすべてのものから》
気が付くと辺りはすっかり宵闇に沈んでいた。
優しい夜気が彩扶錏を包み込む。
《参りましたね、命を奪われかけた結果がこれだ・・・益々あなたが
見上げる空は深い藍。
切れて血の滲む唇に触れた指を、空にかざして呟いた。
「天に星、地に花」
