| HOME | GALLERY1 | GALLERY2 | TEXT | LINK | WEBCLAP | ←お気に召したなら拍手をひとつお願い致します |
第十三話 匂い
比叡山の延暦寺は、京の都の北東、鬼門である艮の方向に位置し、都を鎮護するために建立された。
しかしその遥か昔から、比叡の頂近くには〝鬼族の長〟の邸が鎮座していた。
強い結界が張られていて、余人にはその存在は窺い知れないが、ふとしたはずみに、空間の狭間から篝火の燿が零れ覗き、妖しい世界が垣間見えることがある。
それはまだ年若い修行僧を震え上がらせるに足る光景だった。
霊山・聖域だと信じている場所だから、その動揺は無理からぬことであるが、片や修行を積んだ僧侶達は、この山には人知だけでなく、闇に住まう物をも遥かに越える何かがあるのをはっきり感じている。
それ故の霊山・聖域なのだ。
故に人間と妖しの違いはあれ、同じこの地上に生を受た物が、この場所に魅かれるのは当然のことで、今更ながらに妖しの気配を色濃く感じたからとて動じることもない。
それどころか、この比叡だけでなく霊山、聖域と呼ばれる場所に集うことに於いて、ことごとく人間の方が新参者であることを、声にはしないだけで、薄々気付いてもいた。
広い邸の内でも、主の寝所は一番高い位置にあり、簀子縁から京の都と琵琶湖の両方が望めた。
今は、室内にふたつ、みっつばかりの灯が点っているのみである。
もし簀子縁に誰かが居れば、開け放たれた室内から漏れ聞こえてくる、甘い女の喘ぎに、劣情を刺激されたに違いない。
だが勿論、縁には誰もいないし、寝所には更に結界が張ってあるので、邸内にもその喘ぎが漏れることはなかった。
几帳を廻らせた褥の上に、女がしどけなく横たわっている。
片肘を付いて添い臥した彩扶錏は、空いている片手だけで、その裸同然に乱れた単衣姿に愛撫を与えていた。
だがその眸は目の前の艶姿を映していないばかりか、その耳は切ない喘ぎさえ聴いていなかった。
「・・お館様・・・・お館様」
その声に、彩扶錏はやっと我に返る。
「どうした、羅刹?」
羅刹と呼ばれた鬼女は、美しい女が多い鬼族にあって、一、二を争うほどの美女であった。
そのことを自身でもよく分かっていたので、閨事の最中に相手が他に気を取られている、などということは、たとえそれが己が主であっても耐えられなかった。
まして羅刹は、彩扶錏に心底傾倒していたので、こうして夜伽を仰せつかることは誉れであり、肌を合わせていると、彩扶錏を独占している気になっていたので、己を見詰めてくれない眸に苛立を募らせた。
「わたくしに、なにかご不満がおありでございますか?」
「いや、そのようなことはない」
「なれば、わたくしを見てくださりませ。
もっとかわいがってくださりませ。
そのように上の空ではあんまりでございます」
あざといばかりの媚びをつくる。
「ああ、少し考え事をしていた、許せ」
そう彩扶錏は答え、とりあえず視線を羅刹に注いだが、依然その眸に何も映してはいない。
羅刹はたまりかねて悲鳴を上げる。
「お館様がどなたを想って、上の空なのか存じております。
〝犬の媛〟でございましょう。
何度もあの方の所へ通われているのも存じております。
けれど、ついぞ想いを遂げられたご様子もない。
お館様に靡かぬとは、極端に情が薄いか、他に情夫でもいるのでございましょう。
見目麗しい麒麟を連れ帰ったと聞きますが、なるほどそれなら頷ける。
麒麟は鬼族も及ばぬ絶倫と言うではありませぬか。
加えて超絶技巧を持っているとか、きっとそれが情夫なのです」
「なに?麒麟は超絶技巧の持ち主なのか!」
「〝犬の媛〟はとんだあばずれでなのでございましょう。
誕生の折りに母を死に至らしめ、父親にも疎まれて、あげく殺されかけたという、曰く付きの媛だそうではございま
せぬか。
そんな呪いを宿して産まれたような媛など、お館様にはふさわしくありませぬ」
嫉妬で尖ったその言葉を、黙って聞いていた彩扶錏の眉が、僅かだが歪んだ。
主の微かな
「申し訳ございません、言葉が過ぎました」
「確かにな。
これ以上つまらぬことを
そう言うなり、羅刹の両膝を掴み大きく割り拡げた。
「その唇は、くだらぬ噂より、喘ぎだけを紡いでいればよい」
そして、中心にゆっくりと貌を近づけていった。
「っあ・・・ぁぁ・・・お・や・・かた・・さま・・・・あぁぁぁぁ・・・・」
簀子縁に片膝立てで座っている彩扶錏の髪を、涼やかな微風が揺らしている。
半刻ほど前の濃密な営みの名残で、彩扶錏の躯には女の香が纏わり付いていた。
それを振り払うように、杯の酒をあおる。
どれほど女を抱こうと、満たされなかった。
どれほど強い酒を飲もうと酔えなかった。
心が欲しているのは、唯ひとりの面影であるからだ。

「浅黄水仙の香り・・か」
銀花は己の気配も匂いも自在に消せたが、何も鎧わぬ時は、微かに浅黄水仙の香りがした。
それが銀花本来の匂いなのだろう。
先日、夜着一枚の銀花の側で、彩扶錏はそれを初めて知った。
数日しか経っていないのに、彩扶錏はその匂いが懐かしく、先ほどの淫らな香りが、記憶に残っている銀花の匂いを、かき消してしまいそうで、今すぐ逢いに往きたかった。
新緑に薫る山々の峰に添って、彩扶錏は飛翔していた。
東国の銀花の邸がある杜までは、彩扶錏の飛翔力をもってしても優に一刻半は掛かる。
彩扶錏が比叡山を飛び立ったのが、午之刻頃であった。
今は、すでに申之刻を過ぎているので、普段より飛翔速度が遅いことになる。
気持ちは早く銀花に逢いたかったけれど、先日のことで、まだ怒っているのではと思うと、知らず知らずに飛翔速度が落ちていた。
鬼族の歴代の長の中でも、彩扶錏は最も妖力が強かった。
妖しの間でも〝当代の鬼の長〟を少しでも知るものは無謀な戦いを挑んだりはしない。
大抵の妖しは彩扶錏の名を聞くだけでひれ伏す。
妖力だけでなく、総てに秀いでて、雅な色好みとしても名を馳せている。
その眸に捉えられて否と答えた女人は妖しにも人間にもいない。
それが、唯一想う相手の事となると、からきし意気地がなくなるようだ。
一族のものが、銀花の前の主を見たなら、目を疑うことは必定であった。
はやる気持ちと重い足取りで飛翔していると、前方から鮮やかな妖気が、凄まじい速さで近づいて来た。
彩扶錏の知る限り、あのような早い速度で飛翔出来る妖しは唯ひとりだけだ。
既に相手も彩扶錏に気が付いていた。
そして速度を緩めると、ぶなの巨木の枝に降り立った。
遅れて彩扶錏もその隣に降りる。
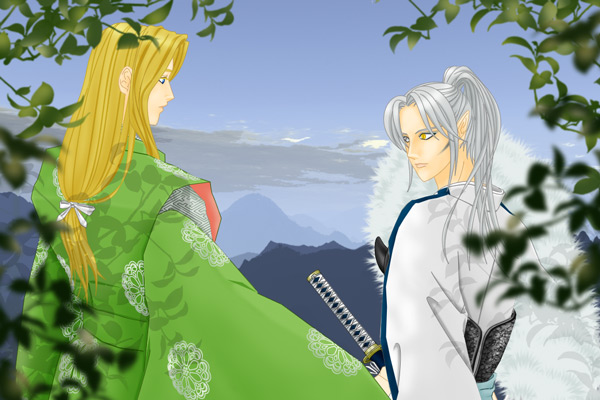
「銀花」
「おや、これは〝鬼の長、夜這いの君〟ではないか」
銀花の嫌みに、彩扶錏はことさらに溜息を付いてみせる。
「銀花ぁ、まだ怒っているのですか?
もう許して下さい、充分反省しておりますよ」
「怒ってなどいない。
だが、今度やったら容赦はしない」
そう言って、喉を掻き切るしぐさをしてみせた。
「二度と夜這いなど致しません。
次は正面から参ります」
「・・・おまえ、本当に反省しているのか?」
「勿論です。
あなたに逢えなかったこの数日が、わたしにとってどれほど永く、切なく寂しかったかお分かりですか?」
銀花は微かに眉間に皺を寄せた。
「ふぅん!
の、わりにはご乱行だったようだな、目の縁か赤いぞ」
彩扶錏は一瞬どきりとするが、そこは流石にさらりと受け答えて見せる。
「冗談じゃありません!
夕べは明け方まで〝長〟としての仕事でほとんど寝ていないのです。
それもこれも早く雑事を片づけて銀花に逢いに来たかったからですよ」
「ほう、長としての仕事な、ご苦労なことだ。
なら、邸で湯を使うが良い」
「湯浴みなら、今朝済ませてきましたが」
「我が湯殿の湯は、不二の山の地脈と繋がる温泉、潔斎にも用いられる霊泉だ。
躯の疲れや汚濁を流してくれる」
「それほどわたしの躯を心配してくださるとは、何だか夢のようです」
「まあ、そういうわけでもないが」
銀花は曖昧に微笑んだ。
「それで、あなたはどちらに?」
「夕刻には戻る」
「お待ちしていて宜しいのですか?」
銀花はうなずくと、飛び立って往った。
邸の主は、先日のことなど気にしていない様子であったが、もう一方の住人は彩扶錏の姿を見るなり、あからさまに貌を顰めた。
「客に向かって、いきなりその態度は何です。
すこぶる礼を失していますよ、蒼鉛」
「客? わたしはまた、不埒な賊かこそ泥かと思いましたが」
「不遜な!」
「そちらこそ厚顔な!」
一瞬火花を散らすが、彩扶錏は一抹の後ろめたさもあったので、ふいと視線を泳がす。
蒼鉛も、やり方はどうあれ、殺生丸や彩扶錏が銀花を心配しての事だと分かっているので、それ以上には嵩高な態度も取れない。
「主は留守です」
「知っている、先ほど逢いました。
夕刻には戻られるとか」
蒼鉛は虚を突かれたような貌で言った。
「銀花様が、そう言われたのですか?」
「そうだ。
それがどうかしたか?」
「いえっ、いえ別に」
銀花は、戻るのは夜中になるから、先に休んでいるよう言い置いて出掛けていた。
となれば、途中で彩扶錏に逢ったために、予定を変えたという事になる。
彩扶錏がいると、心なしか銀花が楽しそうにしているようで、また、蒼鉛の知らない話をしているふたりを見ているのが、近頃、苦痛になって来ていた。
そして苦痛の素がもうひとつあった。
先日の夜、殺生丸の膝枕で眠っている銀花を見た。
蒼鉛も銀花に膝を貸すことはある。,br>
だが、決定的に違うのは、銀花が熟睡していたことだ。
蒼鉛は共に過ごすようになってから、一度として熟睡している銀花を見たことがなかった。
その証拠に、いつもほんの僅かな物音にも素早く覚醒する。
些細な事だと分かっていた。
だが、その些細な事が蒼鉛の心を重くしていた。
大きな溜息をひとつ吐いて、気持ちを切り替えるように仕事に懸かる。
夕刻に主が戻るとなれば、夕餉を用意しておこうと思う。
人間にとっての食事は、日々必要不可欠な物のひとつだが、妖しである銀花や霊獣の蒼鉛は、幾日も飲まず食わずでも活動出来るし、空気中に漂う気を糧にすることも出来た。
けれど蒼鉛は、蓬山での暮らしの中で、朝と夕刻の二回の食事を採っていた。
それは、いずれ王と共に治める国に下り、
生きるために日々食べなければいけない、ということを躯に刷り込まなければ、人々のための政など出来ない。
王も閣僚達も仙であるが、元は人間である。
仙であるから少しくらい食物を口にしなくても死にはしないが、やはり食事は不可欠だ。
そこのところが気を糧と出来る麒麟とは幾分違う。
銀花と蒼鉛は邸を構えてからは日に一度は食事を採るようにしていた。
それは栄養を摂取する目的だけでなく、食事を取りながらとりとめも無いことや、その日の出来事などを話すことが、銀花にとっても蒼鉛にとっても楽しいひとときであるからだった。
蒼鉛自身は完全に菜食だったが、殺生が出来ない他の麒麟と違い、魚をさばくことも野鳥を調理することも出来た。
蓬山の女仙達が料理するところをよく見ていたので、蒼鉛の料理の腕前はかなりのもので、それは、殺生丸の連れている子供のりんや、時折くる犬夜叉の仲間にも大変喜ばれた。
銀花は、りんが齢の割に躯が小さいのを気にしていたので、りんが滞在している間は日に二度の食事の他に、滋養のある木の実を使った菓子などを与えるようにしている。
甘い菓子は、りんを喜ばせたがそればかりでなく、蒼鉛によくなついた。
それは《己の食いぶちは己でなんとかしろ》と、言っている殺生丸を僅かに苛立たせているようでもあったが、当の殺生丸は普段食物を口にすることが無いらしく、この邸で食事をするのを見て、供の小妖とりんが驚いていた。
確かに放浪の途中では食べ物の確保や調理は面倒なことだ。
だが、犬族の邸に居た頃は食事をしていたのだろう、銀花に取り分けてもらって嬉しそうにしていたし、好き嫌いを咎められてもいた。
人間に近い生活を送る鬼族は、むろん飲食の習慣があり、流石に都の文化か、その内容も洗練されている。
彩扶錏が持参する土産はどれも美味であった。
先日の播磨の酒〝月の雫〟も怪しい秘薬さえ入っていなければ、濾しを丹念に施され透明で豊かな香りの美酒であった。
普段美食に慣れているせいで、彩扶錏は好みも味にも煩い。
銀花が戻る夕刻までいるつもりなら、当然のごとく夕餉も相伴するつもりなのだろう。
何故、彩扶錏の食事まで用意せねばならぬのかと腹立たしく思い、いっそこの間の彩扶錏ではないが、一服盛ってやろうかと、思わず不敵な嗤いが零れてしまう。
「蒼鉛、何を嗤っているのです、気持ちの悪い。
おまえ、よからぬことを企んでいるのではあるまいな」
「なっ、ご自分と同じ物差しで計るのはやめていただきたい。
わたしは、夕餉に添える果物が無いなと思案していただけです」
「ほう。
そう言えば来る途中、もう夏茱萸が色づき始めているのが見えたな。
確か茱萸の実は銀花の好物だったか」
「・・・銀花様の好物・・・茱萸の実とはどういうものなのですか?」
「おまえの国には茱萸はないのか?」
「あるやもしれませんが、きっと、名が違うでしょう」
「なるほど、茱萸は木になる親指の先ほどの少し細長く丸い実だ。
少し渋みはあるが、赤く熟すと酸味とほどよい甘みがでる」
「どちらに成っていたのでしょう」
「ここから少し西にある泉のほとりだが」
「その泉なら知っています、行ってみます」
「行くって、おまえは人型では飛翔出来まい」
「ですから、歩いて行きます。
あの泉ならさほどの距離ではありません」
麒麟は、この世の何ものより速く天翔ることが出来る。
しかし、それは麒麟の姿に転変した時だけだった。
銀花や殺生丸は本性から人型になる時、衣なども創り出せるが、麒麟にその力はなかった。
麒麟の姿に転変する時に着ている衣を脱ぎ捨て、行先で人型に転化するなら、衣を持参しなければならないのは些か面倒である。
「なら、わたしも行こう」
「それには及びません。
すぐに戻りますから留守をお願い致します」
「それは構わないが、銀花になるべく邸外に出るなと言われているのだろう?
外には麒麟を狙う妖しがいるぞ」
「銀花様は心配性なのです。
ここに集まる強い妖気のせいか、近頃は辺りに他の妖しの気配はありません。
それに、わたしは戦うことが出来ます」
「噂で聞いている。
己で敵を滅することができる稀なる麒麟らしいな」
「ええ」
一瞬、蒼鉛の眸に銀花のものによく似た寂しげな陰りが過った。
彩扶錏は小角の言葉を憶い出した。
《あの媛は妖しの中にあっても異形、それが麒麟の異形を呼んだのです。
似ておりましょう、あの媛と》
「・・・まあ、気を付けて行くがよい」
麒麟の霊力がどれほど甚大でも、戦うことが出来ないなら意味が無い。
妖しである彩扶錏はそう思う。
だが、蒼鉛のように戦うことが出来たとしたら、己の手で敵を滅っせるとしたら、慈悲の霊獣としての存在価値はどうなるのだろう。
己が足元の草木も踏まない、とさえ言われる麒麟の慈悲の本性と相反する、本来備わるはずの無い殺傷の能力。
その二つは常にせめぎ合うはずだ。
慈悲の本性にだけ忠実でいるわけにはいかない。
何故ならば、蒼鉛にとっては殺傷能力も本性だからだ。
折り合いをつけるのは危うい均衡の上での綱渡りめいている。
それはそっくりそのまま銀花にも言えることだった。
妖しの躯に、古から反目してきた〝古きものども〟の力。
下手をすればより強い方に飲み込まれる。
「確かに似ている」
「誰が似ていると言うのだ。
きさま、ここで何をしている!」
突然の声に、驚いて貌を上げると殺生丸が立っていた。
「いきなりなんです、驚くではないですか」
「ふん、きさまは半妖なみに隙だらけだぞ。
それで〝鬼族の長〟とは恐れ入る」
「少々考え事をしていたのです」
まったく、相変わらず生意気なことだと彩扶錏は思う。
いったいどういう育ちかたをすれば、これほど小面憎くなれるのか。
いくら銀花といえどもその教育方針には一言投げかけたくなる。
「銀花は、夕刻まで戻りませんよ」
彩扶錏の言葉に殺生丸は貌を顰め、一瞬、何かを嗅ぎ分けるような仕草をする。
「姉上が戻られるのを待つつもりか」
「当然でしょう。
蒼鉛やあなたの貌を見にきた訳ではないのです」
「あんなことをしでかして置いて、よくもまぁ邸に入れたものだな」
「それを言うなら、あなたも同罪でしょう」
「きさまと一緒にされてはたまらん!」
「一緒です、寸分
どう言おうがわたし同様、あなたも銀花に夜這いをかけたのは事実なんです。
それがどうです、その傲岸な態度は。
全く反省の色が見えないようですね」
「わたしの夜這いと、きさまの夜這いでは天地ほどの差がある。
それに、何故きさまに反省の色を見せねばならぬ」
「何が天地の差ですか。
口先とあちらの方ばかり一人前になって、他に習得せねばならないことがあるでしょう。
溜まっているなら腰ではなく、躯を動かして発散なさい」
「きさまにあちらの方ばかりと言われるとは思わなかったが、習得せねばならぬこととは何なのだ?
よからぬ秘薬の調合のしかたとかか?
なぁにが発散だ。
薬で眠らせて、あんなことや、こんなことをするつもりであった輩の言う台詞か」
「まさか、あんなことや、こんなことなどするわけが無いでしょう。
あなた、わたしを何だと思っているのです」
「淫乱・淫猥・多淫に好色、大したこともない己が持ち物を振りかざして、絶倫だと嘘吹く色情狂集団の親玉」
「何が淫乱ですか、愛の契はあまねく生物にとって大切なことです。
淫猥とはなんです、多少淫なことも愛の営みの彩り。
多淫とは心外な、周りがわたしをほって置かないだけです。
好色ではなくもっと高尚に
風流を解し美しいものを好む雅な趣味人、それがわたしです。
それに言うに事欠いて、大した持ち物ではないとは何ですか、断じて許せませんね。
だいたいあなた、わたしの持ち物を見たことがあるのですか!
あなたの前で振りかざしたことがありますか!
何なら見せて差し上げるが、それ相応の覚悟をなさい!
それからわたしは嘘吹いてなどいません、正真正銘絶倫です!」
「そんな物、見たくは無いが、やると言うなら受て立つぞ。
返り討ちにしてくれるからそう思え。
後で吠え面をかくのはきさまだ」
「ふふふ、啼くのはあなたの方ですよ殺生丸。
真の絶倫とはどういうものかをその躯をもって知ることになるでしょう」
危ない方向に話が傾いているのに双方気付いていなかった。
その時、あどけない声が響いた。
「絶倫ってなぁに、夜這いってどうするの?
あんなことやこんなことって、どんなこと、殺生丸様?」
一瞬で凍りついたふたりが振り向くと、何時からいたのか貌一杯に好奇心の疑問符を張り付かせた幼女と、あんぐり口を開けた小妖が立っていた。
「絶倫って、りんと似た子?
りんも夜這いしてみたぁい、受けて立ちたぁい」
「・・・邪険、りんを向こうに連れて行け」
「こっこれはお邪魔いたしました」
「お邪魔とはなんだ、邪険?おいっ待て、邪険!」
主の問いには答えずに、何故だか貌を赤らめて、小妖が慌てて子供を引っ張っていく。
「やれやれ〝淫〟の付く言葉を連呼して、まったく教育に悪い。
性教育にはまだ早すぎますでしょう、殺生丸」
「きさまが言うな!
だが、教えておかねばならぬこともある。
それは『きさまの側には決して近付くな』ということだ」
「どういう意味です?
鬼族は都を欲してはいますが、基本的に他の妖しほどには人間を蔑視してはいない」
「だからだ。
鬼族は人間であろうと何であろうと見境なく、年中発情中だろうが」
「聞き捨てなりませんね、それを言うならいつだって臨戦態勢なだけです。
それにわたしがあんな幼子に手をだすと思っているのですか、あなたじゃあるまいし」
「それこそどういう意味だ」
「幼い頃から手元に置いて、何もかも好みのままに染め上げ育てる。
好みの女人を探すより、遥かに確実で、待つ楽しみも味わえる。
『光源氏計画』ですか?!
あなたにしては、なかなかに趣味が良いけれど、すぐ手の届くところに在りながら、時が満ち、可憐に咲かせるま
では手を出したくとも出すわけにはいかない。
欲望と理性の狭間で身悶える地獄ですね。
あなたは自虐趣味がおありなのか、殺生丸」
「なっ、ばっ莫迦なことを言うな!」
「おや、違うのですか?
その否定は『光源氏計画』と『自虐趣味』のどちらに掛かります?」
「どっちもだ!そんな破廉恥な勘ぐりをするのはきさまだけだ」
「えっ?皆そう思ってますよ」
「・・・皆・・・?・・・?」
「ところで、確かにわたしは絶倫ですが、麒麟はそれを上回るそうですよ。
なにせ、馬と鹿の間のような生き物ですから、馬の強靭な太さ強さと鹿の粘りを持ち合わせているそうな。
その上、超絶技巧を有しているとか。
あれを銀花の側に置くのは、やはり危険だ」
「強靭な太さ強さ・・超絶技巧・・・」
脳裏に浮かんだ妄想を殺生丸は慌てて打ち消した。
どうもにも彩扶錏と話していると、己を見失いがちになる。
「その超絶技巧・・いや、蒼鉛はどうした?」
「ああ・・・西の泉に出掛けました」
「姉上とか?」
「いいえ独りでですが、どうかしましたか?」
「来る途中、雑魚妖怪ばかりだが百匹余りが西に向かっていた」
彩扶錏は、聞き終わる前に地を蹴った。
すぐさま殺生丸も続く。
彩扶錏と殺生丸が、森のなかで蒼鉛の姿を見つけた時、まさに百を超える妖怪が襲い掛ろうとしていた。
殺生丸が爪を繰り出そうとするのを彩扶錏が制した。
彩扶錏の態度に、怪訝そうにする殺生丸の前で、蒼鉛は襲い来る妖怪に向けて片手を一閃させた。
すると、妖怪どもは瞬時に砕け散る。
「蒼鉛は戦えるのか」
「そうです。
しかし、見事なものですね」
「・・・確かにな」
殺生丸も同意する。
そういう間にも、蒼鉛は自身はその場を動くこともなく、次々と妖怪を散らしていく。
すぐ頭上から覆い被さるように殺到した妖怪が薙ぎ払らわれた時、彩扶錏は貌を曇らせた。
「ですが、あれでは・・・」
砕け散った妖怪の血が、まともに蒼鉛に降り注いだのだ。 総ての妖怪を滅したときには、辺りは血の海と化していた。
総ての妖怪を滅したときには、辺りは血の海と化していた。
そして、その血溜まりの中で、茫然と佇む蒼鉛の姿があった。
「あやつ、様子が変だな」
「さすがに血に病んだのでしょう」
「血に病む?
あれほどの力がありながらか」
「麒麟は血や怨嗟に病むのです。
蒼鉛には耐性があるようですが、
あれではたまらない」
血溜まりから霧のように血煙が立ち昇っている。
滅されてなお、麒麟の躯を欲するように蒼鉛の周りに凝っているのだ。
そこへ凄まじい風圧が押し寄せた。
彩扶錏や殺生丸はかろうじて踏み止まったが、蒼鉛は倒れるところを寸前で繊手でありながら強い力の腕に支えられた。
「姉上!」「銀花!」
風圧は銀花が地上に降り立った勢いで起こったものだった。
常ならば銀花はそんな降り方はしない。
余程に急いでいたという事であるが、お陰で血煙はきれいに吹き飛ばされていた。
「蒼鉛!」
主の呼びかけに応えはない。
そこに銀花がいることさえ分っていないようだった。
銀花は、蒼鉛の腕を取ったまま、引きずるように歩き出した。
泉のほとりまで来ると、銀花は手荒に蒼鉛の血で汚れた衣を剥ぎ取った。
肌着一枚にすると、そのまま泉の中程まで、ざぶざぶと入っていく。
腰ぐらいの深みに来ると、流れるように腕を動かした。
その動きに連動するように、水が生き物のごとく巻き上がり蒼鉛の頭の上に零れ落ちる。
滾々と湧き出る清浄な泉の水は、銀花の作り出した水流の舞で、蒼鉛に憑いた血と汚濁をきれいに洗い流す。
けれど蒼鉛の様子は変わらず、虚ろな眸は自失したままである。
蒼鉛の首筋に僅かに血が滲んでいた。
銀花は掌にすくった水で流すが、直ぐに血が滲む。
どうやら蒼鉛自身の傷であるらしい。
銀花は、蒼鉛の首筋に貌を寄せると、舌先で血を舐め取った。
「っあ・・」
蒼鉛が微かに呻いた。
さらに唇と舌で傷を優しく舐め上げる。
「んっ・・はっあぁ・・・ぎ・ん・か・・さま・・」
「・・・戻ったか、蒼鉛」
「わたしは・・・・」
「莫迦麒麟が!邸でおとなしくしていろと申したであろう」
「申し訳ございません。
あなたのお命を危険に晒してしまいました」
「そんな事はよい!だが、おまえは己をなんと思っているのだ?」
「は・・い」
「おまえは麒麟ぞ!
いかに敵を滅せるといえど、慈愛の獣である事に違いはない。
その手を汚してはならんのだ!
ここはおまえの居た世界より遥かに血生臭い。
これほど麒麟を狙う妖しが多いとは、我も読み間違っていた」
「わたしをお連れになったのを、後悔なさっておられるのですか?」
蒼鉛の声に悲痛な響きが滲む。
「そうではない。
我と在る時にはその手を汚させたりはしない。
だが、それでも
妖しである我と共に在るとはそういうことだ。
それ故、結界の中に留めている」
「・・わたしは、慈愛の獣である必要がありますか?」
蒼鉛の言葉に銀花は驚く。
「なんだと?」
「麒麟が慈愛の獣である理由は、王が温情を忘れず、民を虐げずに政を行うためものです。
しかし、銀花様は王ではないし、わたしも
だったら、慈愛の獣である必要もない。
汚濁にまみれても構わないのです。
わたしはあなたの為だけの麒麟なのです。
今はまだ、血や怨嗟に病みますが、そのうちもっと耐性をつけて見せます。
だから、わたしを遠ざけないでください。
それに、あなたの匂いに包まれれば、溜まった穢れも浄化されるようです」
銀花はしばらく考え込んでいたが、ひとつ溜息をつくと言った。
「我の麒麟であるなら、命に背くな。
だが、これからはなるべく連れよう」
「はい」
蒼鉛は己よりもずっときゃしゃな主の躯を、大切な大切なものを確認するように、そっと抱き締める。
そして銀花も、己によく似た寂しい魂を、優しく慰めるように抱き返した。
「口を閉じよ!
物欲しそうだぞ彩扶錏」
彩扶錏は、思わず手で口を抑える。
「あなたこそ、目が羨ましそうですよ!」
殺生丸は、ふいと視線を逸らした。
銀花は蒼鉛を連れ、飛翔しようとしていた。
後を追おうとする彩扶錏を殺生丸は押し止めた。
「どこへ行くつもりだ?!」
「銀花の邸に戻るのですよ」
「やめておけ!
行くならせめて、
ここから東に一里ほど行った所に、姉上の湯殿と源を同じくする温泉が沸いている」
「何故です?」
「教えてやる義理はないが、再び姉上の邸に戻るつもりなら別だ。
いいか、犬族は鼻が利く!」
「知っていますが」
「きさまが知っている以上にだ!
よく聞け、匂いで、きさまの昨夜の痴態が何もかも手に取るように知れる」
「なんですって!」
「普通の湯浴みぐらいでは我らの鼻は誤魔化せん!」
「ご忠告有難く頂戴します、殺生丸」
「きさまのためではない!姉上を不快にさせぬためだ。
誤解するなよ、姉上が嫉妬するということではないぞ」
「わかっています。
ですが、もう遅い気がします」
「なにっ」
銀花は飛翔し始めた。
その時、蒼鉛がちらと殺生丸達を振り返った。
「蒼鉛のやつ、今、嗤いましたね」
「ああ、嗤ったな」
「なんですあれは、勝ち誇ったように」
「まったくだ」
「珍しく意見の一致をみましたね」
「後にも先にも一度きりであることを願うがな」
「蒼鉛は文字通り、黒麒麟というわけですね」
「腹黒麒麟と言うべきか」
皮肉な調子でふたりは呟いた。
第十三話 匂い おわり
この後のお話をちょっと書いてみました。
あぶない匂いを漂わせて・・・よい子の皆さんは決して入ってはいけません! 第十三後話 危ない遊技